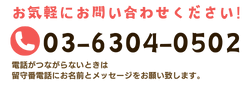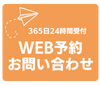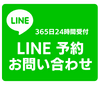大豆食品摂取と子宮内膜症リスクの関係
ハーバード大学の大規模研究から「大豆食品を適度に摂ると子宮内膜症のリスクが低下する可能性」が示されました。
🍀なぜ大豆が関係するのか?
大豆には 大豆イソフラボン が含まれており、女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをします。
子宮内膜症はエストロゲン依存性の病気のため、イソフラボンがエストロゲン受容体に結合することで「過剰な刺激を和らげる」可能性が考えられます。
📊 研究内容
- 1991~2021年、ハーバード大学による看護師コホート研究
- 対象:82,084名の女性
- 食事調査で大豆摂取量を計測、腹腔鏡で診断された子宮内膜症の発症を追跡
- 結果:
- 大豆摂取が週1回増えるごとに子宮内膜症リスクが8%低下
- イソフラボン摂取もリスク低下と関連
🌱 体外受精との関係
別の研究(EARTH研究)では、大豆食品を摂取している女性の方が体外受精の出産率が高い傾向にありました。
ただし「たくさん食べれば良い」というわけではなく、適量で効果的 と考えられています。
🍽 日本人の摂取量は?
厚労省の調査では、日本人女性(30代)の大豆食品摂取量は平均39.1g/日。
例:
- 納豆1パック(45g):イソフラボン約35mg
- 豆腐1丁(300g):約80mg
- 豆乳1パック(200ml):約40mg➡ すでに研究で有効とされる量を、日本人は普段の食事で自然に摂取できています。
普段ほとんど食べない方は、週に3回以上を目安に大豆食品を取り入れると安心です。
➡ すでに研究で有効とされる量を、日本人は普段の食事で自然に摂取できています。
普段ほとんど食べない方は、週に3回以上を目安に大豆食品を取り入れると安心です。
🌸大豆食品を摂りすぎるデメリット
① ホルモンバランスへの影響
- 大豆イソフラボンはエストロゲン様作用を持つため、過剰に摂ると月経周期が乱れる可能性 があります。
- 特にホルモン感受性のがん(乳がん、子宮体がんなど)治療中の方は、主治医に相談が必要です。
② 甲状腺機能への影響
- イソフラボンの摂りすぎは、甲状腺ホルモンの働きを邪魔する可能性があるとされています。
- 健康な方なら通常食事レベルで問題ありませんが、甲状腺疾患のある方は要注意。
③ 消化器への負担
- 納豆・豆乳・豆腐を一度に大量に摂ると、お腹が張る、消化不良、下痢 などが起こることがあります。
④ 摂取量の目安
厚生労働省「大豆イソフラボンに関するQ&A」では、
- 上限の目安:1日70〜75mg程度(サプリなどで集中的に摂る場合)
- 食品からの摂取であれば、通常の和食中心の食生活なら問題なし。
※参考:納豆1パック(45g)=約35mgイソフラボン
➡ 納豆2パック+豆乳200mlを毎日続けると上限を超える可能性あり。
🌱まとめ
- 大豆食品を適度に摂ると子宮内膜症のリスクが低下する可能性がある。
- 普通の食事で納豆・豆腐・豆乳をバランスよく摂る分には安全。
- サプリや加工品で“意識的に大量摂取”するのは控える。
- 甲状腺やホルモン関連の病気がある方は、主治医に確認を。